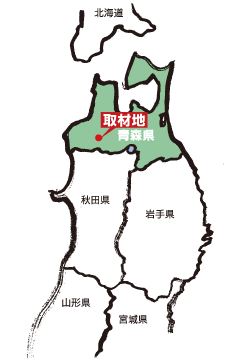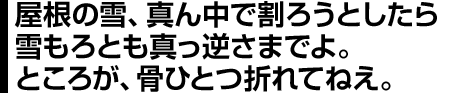
道路の両側に積み上がった雪の壁を抜けて、沢田生活改善センターに入ると、搗きたてのヨモギ餅の心和む香りが漂う。「塩っこさ入れると、やっこい餅になるだびょん」「したらば、ひれや(それなら、入れて)」「ありゃあ、やっこ過ぎだべひゃ」。大澤きみさん(75)が、あんこを包んだヨモギ餅を取り分けると、大きすぎるの柔らかいの、と言っては皆で笑う。地元の女性六人が、祭りで販売するヨモギのあんこ餅と神明様にお供えする紅白餅作りに忙しい。
屋外では、今夕に迫った「沢田ろうそくまつり」の準備で、男性たちが自分の背丈よりも高く積もった雪と格闘している。神明宮へ上る急斜面をカニ歩きで踏みしめ、スコップで階段を刻む。ピチピチと水滴の落ちる音に混ざって、時折、ドスンと落下音が響く。気温五度。雪が解け、鳥居脇の欅(けやき)や神明宮岩屋堂に覆い被さる大岩に積もった雪が勢いよく落下しているのだ。町内会長の種澤満さん(60)が、祈るように神明宮を見上げる。ひと月前、公民館の屋根の雪下ろしをしていて、十五メートル下の作沢川に転落した。
「今年は、雪の量が半端じゃねえべや。あん時もよ、屋根の雪を真ん中で割ろうとした瞬間、雪もろとも真っ逆さまでよ、死んじまったべなあって思ったの。ところが、骨ひとつ折れてねがった。神明様さ守ってくれたんだべや」
四百五十年の歴史を刻んできた「沢田ろうそくまつり」に、怪我人を出すわけにはいかない。
平成十八年に弘前市と合併した旧相馬村は、北西に岩木山、南西に白神山系が連なるりんご栽培の盛んな津軽平野南西部の山間地だ。奥相馬と呼ばれる十世帯が暮らす沢田集落で、今年も旧暦の小正月(二月六日)に、神明宮本祭の前夜祭として「沢田ろうそくまつり」が開催された。
午後五時過ぎ、岩屋堂前の急斜面に「ほたる」をイメージしたろうそくが一面に灯った。腹の底から熱気を呼び起こす登山囃子を打ち鳴らす楽隊を先頭に、松明行列が雪の階段を上る。参拝者がろうそくを手に岩屋堂へ向かう。拝殿前の大岩にろうそくの灯りを立てると、十五夜の月が岩間からお堂の中を照らしていた。
|
|
|