 |
| 下井手用水終点の棚田。緑川の谷を挟んだ対岸に九州山地が連なる |
集落の入口に鎮座する白石天満宮の銀杏が、日に日に黄色く染まっていた。その大木の下を運搬機のエンジン音を響かせて安達義光さん(73)が田んぼへ向かう。ひと月前に掛け干しを終えた田には、切り株から緑色のひこばえが十センチほど伸び、朝霜で輝いている。土手に積まれた堆肥の山を、義光さんがスコップで崩すと、ハエが勢いよく飛びまわった。
「町で牛ば養うとるもんがおって、うちの藁と堆肥を交換したったい。じるか(水分が多い)ばってん、文句は言えんよ」
冬を控え、田の土に藁や堆肥を混ぜて耕す「冬鋤き」の準備だ。運搬機を使って隅から順に堆肥を撒く。三往復すると汗が吹き出し、義光さんはシャツ一枚になった。
阿蘇南外輪山と九州山地に囲まれた熊本県東部の上益城郡山都町白石地区。五老ケ滝川と笹原川、それに千滝川の切り立った深い渓谷に囲まれている白糸台地は、農業用水はおろか飲み水にも苦労した歴史がある。
江戸時代末期の嘉永七(一八五四)年に石造水路橋「通潤橋」が完成し、上井出と下井出の二本の灌漑用水路が通ったことで、白糸台地にも棚田を拓くことができた。十四世帯が暮らす白石地区は、通潤橋灌漑用水路の恩恵を受ける棚田の終点にある。
後藤一誠さん(78)と富美子さん(77)夫婦が、棚田を見下ろす小さな畑で玉葱を植えていた。雑草を生やさず土を保温するために被せた黒ビニールのマルチに、棒で穴を開けるのが富美子さん。一誠さんは手際よく苗を埋め込んでいる。
「新大豆もでけたし、こん冬は自分で納豆ば寝しちみろかなって思いよっとですたい。買うた納豆はネヤネヤで匂いのすったい。うちでしたつは、そりゃあ美味しかばい。あん山の斜面にカマ(穴)があるけんな。中に藁ば敷いち、二日ばかり寝かして菌ば付けるたい」
イナゴが飛びはねているお椀を伏せたような小山に、安達家と後藤家の墓が並んでいる。見晴らしがよく日当たりに恵まれたご先祖様の足元で、納豆を寝かせるという。夕刻、日が陰ると、冬支度を始めた集落に、紅葉の深まる山から冷気が下りて来た。
|


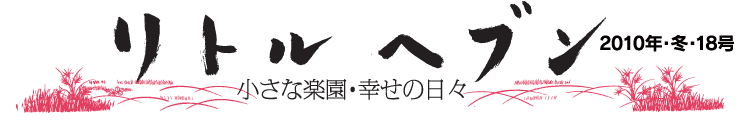
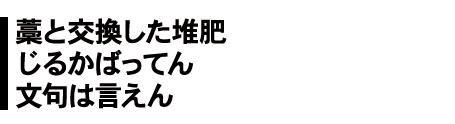
 TOP
TOP
