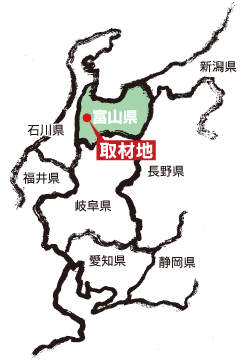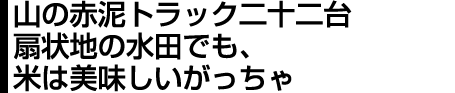|
ひょろりと頼りない植えたばかりの苗を揺らして南風が吹き抜ける。五月初旬、陽射しは強くとも立山連峰の残雪を通ってきた風は、まだ冷たい。米どころとして知られる砺波(となみ)平野で、兼業農家の安念(あんねん)則夫さん(56)一家が揃って田植えをしていた。
雪解け水が勢いよく流れる用水に、三男の匠海くん(11)が片足を突っ込んで空になった苗箱を洗う手伝いをしている。苗が入っていた箱の泥を洗うのは女性の仕事。
「こん子は、上手に洗うてくれるがやで。私は縁だけちょっこ洗うときゃあええが」と、玲子さん(82)が孫の手伝いに目を細める。則夫さんは、六条植えの田植え機に乗りっぱなしだ。昭和三十七年に行われた大規模な圃場整備で、砺波平野の水田は一区画が三十アールほどの大きな田になった。
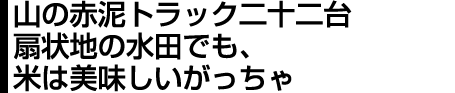
「こん田は、山の赤泥が入ってん。十トントラックで二十二台分も山の土を入れたで、米は美味しいがっちゃ」。則夫さんは、六ヘクタールの田植えのために、半月ほど休暇をとって準備から始めた。田植えが終わり次第、会社勤めの生活に戻る。
三時のお茶は、農道に肥料袋を置いて、その上に揃って腰掛けた。近くで青々と波打つ麦畑に急降下するヒバリを見ながら、玲子さんがぽつりと言う。
「前は今頃、近所のみんなが田に出ておったが、今日は、うちらだけや。どこんちも農事組合に田あ預けて、顔見んようになったが」
●●●
富山県西部に位置する砺波市。砺波平野は、飛騨高地を源流とする庄川が西に東に流れを変えて、長い歳月が作り上げた扇状地だ。砂や小石が堆積している土地だが、庄川の豊かな水量と先人が築き上げた網の目のような用水路のおかげで、水田の中に家が点在する「散居村(さんきょそん)」といわれる集落の形態ができあがった。
高台から砺波平野を眺めると、水を張った田が太陽の光を受けて鏡のように輝く。点在する屋敷は、ぽつりぽつりと水に浮かぶ小島のようだ。各家の南西側には、カイニョと呼ばれる杉やケヤキなどの屋敷林が植えられ、立山連峰から吹き下ろす強風から屋敷を守っている。広い水田と小さな森のある暮らし。散居村の家屋敷は、水と緑に囲まれた小宇宙なのだ。
|